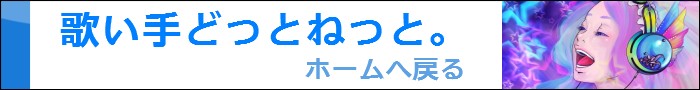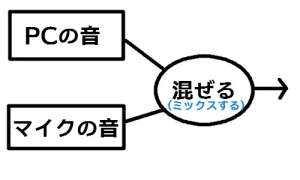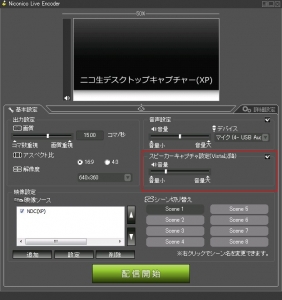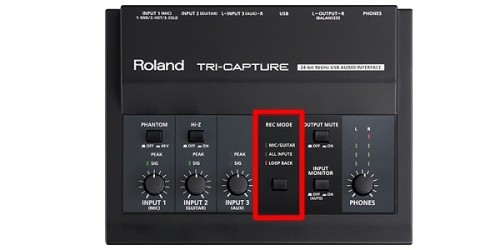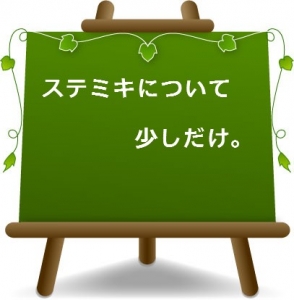
今回は少しだけ、ステミキについてお話します。
解説ではありません、あくまでお話です。
以前は生放送というと、このステミキが必ずと言っていいほど付いて回りました。
ステミキというのは、ステレオミキサーの略です。
つまり、ミキサーのことです。
(ステレオはちょっと忘れましょう)
簡単に言うと、PCで鳴っている音とマイクで拾った音を、混ぜる(ミックスする)機能のことです。
こういう感じに。
そして、それを放送に乗せるという感じです。
以前は、全部は理解できていなくても、少なくとも、
- 自分のPCにステミキがあるか?
- 自分のPCでステミキを使うにはどうしたらいいか?
くらいは分かっていないとダメでした。
ですが、今は、niconico live encoder(以下NLE)が使えれば問題なくなりました。
NLEにほぼ同様の機能が付いたからです。
もちろんオーディオインターフェースがあれば、NLEの機能も必要ありません。
(厳密には、オーディオインターフェースにMIX機能があればなのですが)
ちなみに、NLEのステミキのような機能は、スピーカーキャプチャといいます。
上の赤枠の部分にスピーカーキャプチャの設定があります。
このチェックを入れると、PCで鳴っている音を放送に乗せることができます。
スピーカーキャプチャは、PCのスペックによっては、放送で音楽とマイクの間にラグが出ることがあります。
ですが、ステミキを理解するのは結構大変なので、今のPCの状態ですぐステミキが使えない限り、ステミキ機能を使うのは、あんまり現実的ではありません。
それならば、いっそオーディオインターフェースを買ってしまった方が楽です。
機能を利用する難易度は、
NLE < オーディオインターフェース <<<<< PCのステミキ機能
みたいな感じです。
それでもまだ、ステミキ機能を使う! という方は、この記事の「それでもPCのステミキを使いたい人へ」を見てください。
ステミキできるオーディオインターフェースは?

オーディオインターフェースでも、全ての機種でステミキ機能が使えるわけではありません。
中には使えないものもあります。
例えば、今でも人気のあるUA-4FXですが、UA-4FX自体にはステミキ機能はありません。
配線の仕方でステミキっぽいことができる、というだけです。
ステミキ機能が付いているオーディオインターフェースは沢山ありますが、ここでは二つだけ紹介します。
 |
![]()
1つはTRI-CAPTUREです。
UA-4FXの後釜ですね。
この機種では、LoopBackという機能が付いていて、それがステミキ機能にあたります。
上の画像の赤枠の部分に、REC MODEがあります。
ここの、【LOOP BACK】がステミキ機能です。
 |
![]()
もう一つが、QUAD-CAPTUREです。
TRI-CAPTUREのさらに後釜ですね。
機能的にはこちらの方がTRI-CAPTUREよりもずっとすぐれています。
この機種には、MIXのツマミが付いています。
上の画像の赤枠の部分にMIXの機能があります。
これがステミキ機能にあたります。
ツマミをINPUTに振れば、マイクの音が大きく、PLAYBACKに振れば、PCからの音が大きくなります。
程よい音量を探しましょう。
オーディオインターフェースだと、ステミキのON/OFFも簡単なので、凸待ちやコラボなんかでも重宝します。
それでもPCのステミキを使いたい人へ
それでもなお、PCのステミキ機能を使いたい!
もしくは、それしか方法がない! という方がいるかもしれません。
そういう方には、こちらの動画をオススメします。
上がWindows Vista, 7, 8 用の動画、下がXP用の動画になります。
非常に丁寧な内容なので、ステミキを使いたい人は見てください。
以上でステミキについてのお話は終了です。
次回からは、何回かに分けて、生放送の手順を追ってみていきましょう。
関連記事